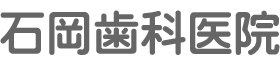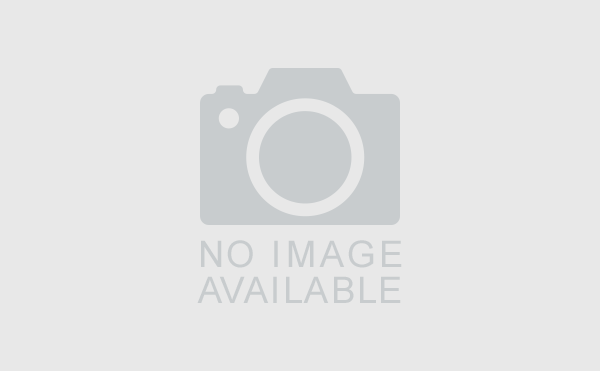矯正治療でなぜ歯が動くのか
愛媛県松山市の歯医者、石岡歯科医院の院長 石岡 亮です。
今回は、「矯正治療でなぜ歯が動くのか」についてお話をしていきます。
【目次】
1.はじめに
2.矯正治療で歯が動く仕組みとは?
3.歯と骨をつなぐ「歯根膜」の役割
4.圧迫と牽引による細胞の働き
5.骨が溶ける?破骨細胞の役割
6.新しい骨が作られる?骨芽細胞の役割
7.力のかけ方と矯正治療の工夫
8.歯が動くスピードと治療期間
9.歯が後戻りする理由と対策
10.まとめ
1.はじめに
矯正治療は「ワイヤーやマウスピースで歯を引っ張っているだけ」と思われがちですが、実際には歯や骨、細胞が複雑に関わる「生物学的な現象」です。
今回は、矯正で歯が動く原理を、できるだけ分かりやすくお伝えしていきます。
2.矯正治療で歯が動く仕組みとは?
歯は顎の骨(歯槽骨)に直接埋まっているのではなく、「歯根膜」という薄いクッションのような組織を介して支えられています。
矯正器具で歯に力を加えると、この歯根膜に変化が起き、結果的に骨が溶けたり作られたりして、歯が少しずつ移動します。
3.歯と骨をつなぐ「歯根膜」の役割
歯根膜は、厚さわずか0.2mm程度ですが、非常に重要な組織です。
歯根膜の役割としては、
・クッションのように噛む力を分散する
・神経や血管が通り、歯の健康を保つ
・歯と骨をしっかりと結びつける
などがあり、矯正の力が加わると、この歯根膜が「圧迫される側」と「引っ張られる側」に分かれます。
ここから歯の動きが始まります。
4.圧迫と牽引による細胞の働き
矯正力によって歯根膜が 圧迫される側 では、血流が減少し、破骨細胞が集まって骨を溶かす準備をします。
一方、引っ張られる側 では、歯根膜が引き延ばされ、血流が豊富になり、骨芽細胞が活性化して新しい骨を作り出します。
つまり、矯正とは「骨を溶かす」と「骨を作る」という2つの現象がバランスよく起きている状態なのです。
5.骨が溶ける?破骨細胞の役割
矯正で歯が動くうえで欠かせないのが 破骨細胞 です。
破骨細胞は、骨を溶かしてスペースを作る細胞です。
歯が動く方向の圧迫側に多く現れ、顎の骨を吸収し、歯が移動するための道を開いてくれます。
6.新しい骨が作られる?骨芽細胞の役割
破骨細胞が骨を溶かしたままでは、歯がグラグラしてしまいます。
そこで働くのが 骨芽細胞 です。
引っ張られる側に集まった骨芽細胞は、新しい骨を作り出し、歯が移動した後にしっかり固定されるようにします。
7.力のかけ方と矯正治療の工夫
矯正治療では、この「骨を溶かす」と「骨を作る」のバランスを大切にしています。
・力が強すぎると → 歯根膜や血管が過度に圧迫され、歯が動かない、あるいは歯根吸収のリスクが高まる
・力が弱すぎると → 細胞の反応が不十分で歯が動きにくい
そのため、矯正は「弱く、持続的な力」を加えることが理想とされています。
8.歯が動くスピードと治療期間
一般的に、歯は 1か月に0.5~1mm程度 動くとされています。
矯正治療の期間が数年に及ぶのは、このスピードに合わせて安全に進めるためです。
また、年齢や骨の硬さ、個人の代謝によってもスピードは変わります。
9.歯が後戻りする理由と対策
矯正後に歯が元の位置に戻ろうとする「後戻り」も、歯根膜や骨の働きが関係しています。
矯正で移動した直後は、骨がまだ安定していないため、歯は動きやすい状態です。
これを防ぐために「リテーナー(保定装置)」を使用し、新しい骨がしっかり固まるまで歯を固定します。
10.まとめ
矯正治療で歯が動く原理は、単なる「力づく」ではなく、歯根膜・破骨細胞・骨芽細胞が関わる生物学的なリモデリング現象です。
・圧迫側では破骨細胞が骨を溶かす
・牽引側では骨芽細胞が新しい骨を作る
この繰り返しで歯は少しずつ動いていきます。
矯正は科学的な裏付けに基づいた治療であり、だからこそ安心して取り組むことができます。
歯が動くメカニズムを理解することで、矯正治療への不安が軽減し、前向きに治療に臨めるのではないでしょうか。
当院では矯正治療を行っておりますので、矯正治療に興味のある方はぜひ当院へご来院ください。